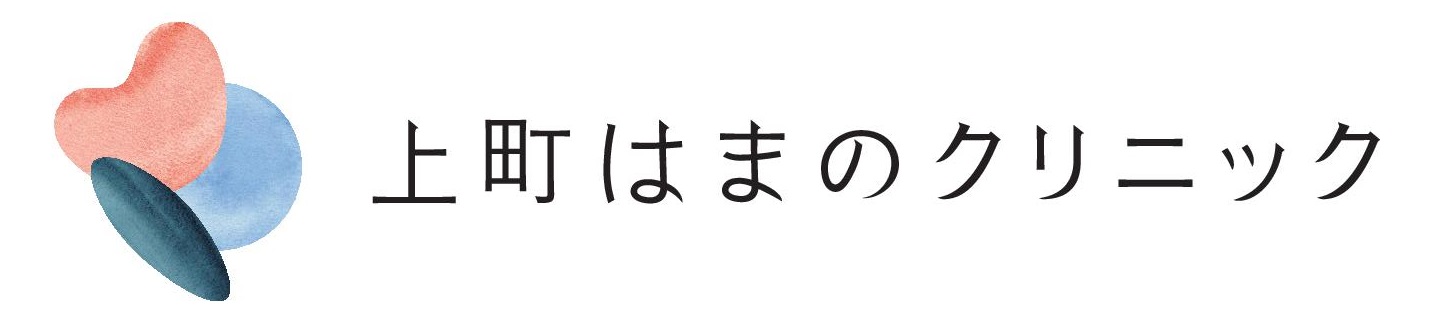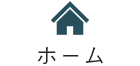「むくみ外来」を開設
 むくみは体の中で余った水分が蓄積すると生じます。塩分や水分の摂りすぎ、食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎ、寝不足・寝過ぎ、腎臓・心臓・肝臓・甲状腺などの働きの低下、足の血流の悪化などがむくみの原因となります。個人差はあるものの、朝起床した際は顔に、夕方になると足にむくみが現れる人が多いです。むくみがない場合、指で肌を押してもすぐ元通りになりますが、むくんでいると凹んだまま元に戻るのに時間がかかります。むくみが気になる方は当院のむくみ外来にご相談ください。
むくみは体の中で余った水分が蓄積すると生じます。塩分や水分の摂りすぎ、食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎ、寝不足・寝過ぎ、腎臓・心臓・肝臓・甲状腺などの働きの低下、足の血流の悪化などがむくみの原因となります。個人差はあるものの、朝起床した際は顔に、夕方になると足にむくみが現れる人が多いです。むくみがない場合、指で肌を押してもすぐ元通りになりますが、むくんでいると凹んだまま元に戻るのに時間がかかります。むくみが気になる方は当院のむくみ外来にご相談ください。
むくみを解消するには、原因を特定してその治療を行う必要があります。血管、心臓、腎臓などに異常が発生し、むくみが現れている場合もあります。原因を特定し、それに応じた治療を行うことが重要と考えております。
むくみ外来はこのような方におすすめです

- 足がだるい、重い、疲れやすい、痛い
- 顔、まぶた、腹部、手、ふくらはぎ、足がむくむ
- 階段や坂道で息切れしてしまう
- 長い時間、同じ姿勢を取り続けることがよくある(立ちっぱなし、座りっぱなし)
- むくみがなかなかとれない
- 何日もむくみなどの症状が続く
- 足の血管がボコボコしている
- 突然、体重増加した
- 疲労感
- 尿が少ない、出しにくい
むくみの原因・考えられる病気
一過性のむくみは生活習慣によって生じたものである場合が多いです。一方、慢性化したむくみは何らかの病気が原因で現れている可能性があります。治療がすぐ必要なケースもあるので注意しなければいけません。
横になった際に足に送られた血液は重力に逆らう必要がなく、心臓まで戻っていきます。しかし、起きた状態だと足が最も下にあるため重力によって水分が足に溜まり、夕方以降にむくみを感じる傾向があります。これが一過性のむくみの原因です。
一過性のむくみの原因
長時間の立ち仕事や
デスクワーク
立ち仕事やデスクワークでふくらはぎを動かさずに同じ姿勢を続けると、足の静脈内の血液の流れが停滞して心臓に血液が戻りにくくなり、むくみが生じます。
ふくらはぎの筋力の衰え
ふくらはぎのポンプ機能は足の静脈内の血液が心臓へ戻るのを助けています。運動不足による筋力の衰えで、その働きが低下すると、むくみやすくなります。
自律神経の乱れによる
代謝機能の低下
汗をかくのは体温調節に必要な水分代謝によるもので、自律神経が深く関わっています。自律神経は、温度が一定に保たれた部屋などに長くいることでその機能が衰えてしまい、水分代謝機能の低下に繋がってむくみが現れます。
ダイエット・偏った食生活
ダイエットによって栄養が偏り、タンパク質の不足などが起こると、ふくらはぎの筋力が低下し、むくみに繋がります。またカルシウム、カリウム、マグネシウムなどのミネラル、たんぱく質、ビタミンB1が不足するとむくみが現れます。
塩分の過剰摂取
塩分は体内の水分を一定に保つ働きがあります。塩分過多になることで余った水分を体外に排出するのが難しくなり、むくみに繋がります。
お酒の飲み過ぎ
アルコールを摂取することで血管の中は脱水状態になります。お酒を飲み過ぎると体内の水分は失われ、血液はドロドロになるため、体は血液を薄めようと水分を多く血管の中に取り込むように働きます。この働きによってむくみが生じます。
ホルモンバランスの変化
生理前は黄体ホルモンの影響で体内の水分が増加してむくみやすくなります。
また、妊娠によってホルモンが変化し、よくむくみを感じるようになります。
慢性的・病気によるもの
心不全
心臓に何らかの異常が発生して、全身に血液を送り出す機能が低下すると、腎臓などの臓器への血流が低下し、それを補うために体が塩分と水分を溜め込もうとします。それによってむくみが生じます。
肝不全・腎不全
血液の中にあるアルブミンというたんぱく質が、血液内の水分の量を一定に保つ働きをします。アルブミンは肝臓で合成される物質で、肝不全によって肝機能の低下が起こるとアルブミンの量が減少し、むくみが生じます。
また、腎不全で腎機能が低下した場合、体内の水分の排泄がうまくいかなくなり、タンパク質が尿中に排出されてしまうことにより、水分が蓄積されてむくみに繋がります。
リンパ浮腫
体中に通っているリンパ管にはリンパ液が流れています。リンパ液の流れが停滞して手足にリンパ液が溜まることをリンパ浮腫と言い、がんの手術を行った後に発生する傾向があります。乳がんの手術で行われるリンパ節の切除や放射線治療によって、リンパ液の流れが滞ることでむくみが現れます。術後すぐ症状が現れる場合もありますが、術後数年経過してから急に発症する場合もあります。
がんの術後以外で、原因不明のものは「特発性リンパ浮腫」と診断されます。リンパ浮腫は放置しても自然治癒が見込めないことが多く、突然症状が酷くなり、痛みや熱を感じる急性リンパ管炎を発症することもあります。
下肢静脈瘤
足の静脈には静脈弁が付いており、心臓に戻った血液の逆流を防ぐ役割を担っています。静脈弁の働きが悪くなると、血液が滞ってしまい、むくみが生じます。診断は下肢静脈エコー検査などで行います。
深部静脈血栓症
(エコノミークラス
症候群)
深部静脈血栓塞栓症は、長時間同じ姿勢でいること(病気や手術後で起きられない、飛行機やバスの長距離移動など)が原因で、足の静脈に血栓(血液の塊)ができた状態です。血栓によって血液が心臓に戻りにくくなるため、足にむくみが生じます。血栓ができないように、弾性ストッキングの着用、こまめな水分摂取、足を動かすといった対策が必要です。
甲状腺機能低下症
肌を指で押して元通りになるようなむくみが現れます。朝起きた際にむくんでおり、お昼くらいまでには少し落ち着くケースが多いです。首の前面にある甲状腺というホルモンを出す臓器の機能が低下することで生じ、血液検査によって診断可能です。
むくみ外来で行う検査
- CT検査
- レントゲン検査
- 超音波検査(エコー検査)
- 心電図検査
- 血液検査
- 尿検査
むくみ外来で行う治療
原因疾患の治療
腎不全、心不全、甲状腺機能低下症、下肢静脈瘤、肝硬変、リンパ浮腫、ネフローゼ症候群といった疾患が確認された場合、その治療を優先して行います。
食事療法
塩分やお酒の摂りすぎがあれば、生活習慣を改善していただきます。血流を促進するビタミンEが豊富な食品や塩分の排出を促進するカリウムが豊富な食品を積極的に食べるようにしましょう。
運動療法・ストレッチ
軽いジョギングやウォーキングといった運動を毎日継続し、ふくらはぎの筋肉をつける筋力トレーニング(カーフレイズ)を行いましょう。デスクワークや立ち仕事が多い場合、30分に1回は休憩をお取りください。その間に足首のストレッチやつま先立ちで体をほぐすようにしましょう。
医療用弾性ストッキング
薬局などで医療用弾性ストッキングを購入して、足の血流を促し、むくみを改善するのもお勧めです。
むくみの解消法
むくみの原因が病気以外の場合、生活習慣を見直してむくみを予防する必要があります。予防に取り組むことで、もしむくみが生じたとしても、軽いもので済みます。
マッサージ・ストレッチ
ふくらはぎをほぐすことで、蓄積した水分や血液が心臓に戻りやすくなります。ふくらはぎをなでるようにほぐしてリンパの流れを促すのがポイントです。また、ふくらはぎのヒラメ筋や腓腹筋をほぐすようにストレッチすると、血行改善や血行促進に効果的です。
塩分摂取は適度に
ビタミンEを
摂取しましょう
むくみを予防するためには、塩分を摂りすぎないように食生活を改善する必要があります。塩分を摂りすぎると、より多くの水分を欲するため、むくみが悪化しやすくなります。お菓子類やカップラーメンなどはできるだけ避けてください。また、塩分を体の外へ出す働きがあるカリウムや、血流促進に効果が期待できるビタミンEが含まれる下記のような食材を積極的に食べるようにしましょう。
カリウムが豊富な食材
バナナ・アボカド・はっさく・もも・干し柿・いよかん・りんご・キウイ・昆布・ひじき・ほうれん草・にんにく・じゃがいも・納豆など
ビタミンEが豊富な食材
ピーナッツ・アーモンド・アボカド・抹茶・ほうれん草・かぼちゃ・モロヘイヤ・バジル・赤ピーマン・卵・たらこ・しそ・いわし・ごまなど
運動
筋力アップのため階段の昇降、ウォーキングなどの運動やカーフレイズなどふくらはぎの筋肉を鍛えるトレーニング行い、血流を促しましょう。また、足首を回してほぐす、寝る時に薄いクッションを足の下に置いて足を高くするのも、むくみ解消の効果が期待できます。