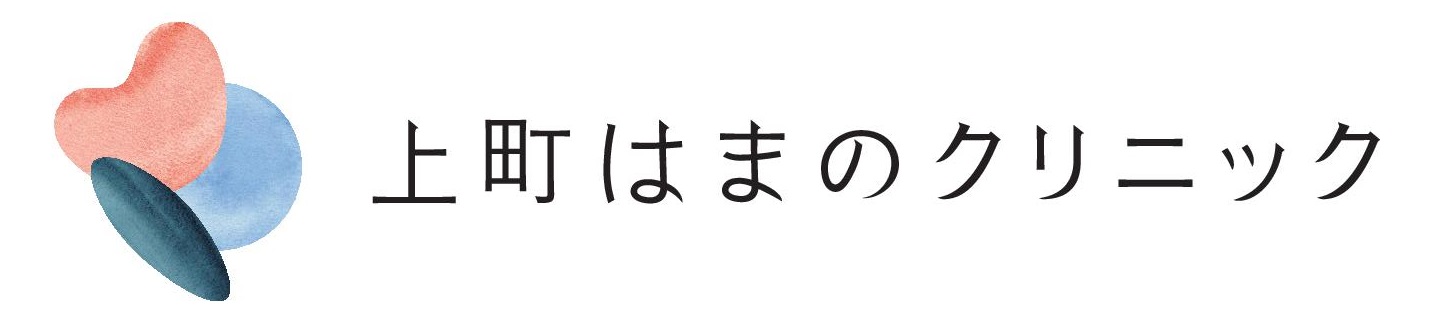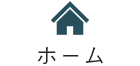- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは
- 睡眠時無呼吸症候群の症状チェック
- 睡眠時無呼吸症候群の原因
- 睡眠時無呼吸症候群が引き起こす主な病気
- 睡眠時無呼吸症候群は何科を受診すべき?
- 自宅でできる睡眠時無呼吸症候群の検査
- 当院の治療内容
- 睡眠時無呼吸症候群の対策と予防
- よくある質問
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは
 睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)とは、睡眠中に何度も呼吸が止まったり(無呼吸)、弱くなったり(低呼吸)する病気です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)とは、睡眠中に何度も呼吸が止まったり(無呼吸)、弱くなったり(低呼吸)する病気です。
自分では気づきにくい疾患ですが、深刻な健康被害を引き起こすことがあり、早期発見と治療が非常に重要です。代表的なタイプは「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)」で、のどの筋肉の緩みや舌の沈下により、空気の通り道(上気道)がふさがれてしまうことで起こります。また、脳の呼吸中枢が正常に働かなくなる「中枢性睡眠時無呼吸症候群」もありますが、こちらは比較的まれです。
SASは、日中の強い眠気や集中力の低下を引き起こすだけでなく、高血圧、糖尿病、心不全、脳卒中など、重大な生活習慣病のリスクを高めることが知られています。いびきや日中の眠気、起床時の頭痛などの症状がある方は、早めの受診をおすすめします。
睡眠時無呼吸症候群外来を開設しました
上町はまのクリニックでは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)に特化した外来を新たに開設しました。
「いびきが気になる」「日中の眠気が強い」「無呼吸を指摘されたことがある」などの症状をお持ちの方に向けて、自宅でできる検査から、専門的な診断・治療まで一貫して対応しています。
また、当院には循環器・総合内科・呼吸器・糖尿病・内分泌の専門医が在籍しており、睡眠時無呼吸症候群と深く関係する高血圧・心不全・糖尿病などの生活習慣病も含めて多角的な視点で診療を行っています。
「いびきは病気のサインかもしれない」「パートナーのいびきが気になる」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。


睡眠時無呼吸症候群の症状チェック
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、自覚しにくい病気ですが、以下のような症状がある方は注意が必要です。当てはまる項目が多いほど、SASの可能性が高くなります。ひとつでも気になる症状があれば、お早めにご相談ください。
夜間・就寝中の症状
- 大きないびきをかくと言われたことがある
- いびきが途中で止まり、しばらくして「ガッ」と息をするような音がする
- 寝ているときに呼吸が止まっていると指摘されたことがある
- 健康診断で血圧、脂質、血糖値、尿酸値が基準値を外れていた方
- 寝汗をかく、何度も目が覚める
- 寝ても熟睡感がない
朝の症状
- 起床時に頭痛や喉の渇きがある
- 十分な睡眠時間を取っても疲れが取れない
- 朝起きるのがつらい
日中の症状
- 日中に強い眠気がある
- 会話中や運転中でもうとうとしてしまう
- 集中力や記憶力の低下を感じる
- 気分がすぐれない、イライラしやすい
これらの症状は、単なる「疲れ」や「加齢」と思われがちですが、睡眠中の呼吸障害が原因であることも少なくありません。
とくに、「いびき」と「日中の強い眠気」の両方がある場合は、睡眠時無呼吸症候群の典型的なサインです。
睡眠時無呼吸症候群の原因
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の多くは、「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)」と呼ばれるタイプで、睡眠中に気道(空気の通り道)がふさがれることによって起こります。では、なぜ気道がふさがれてしまうのでしょうか?主な原因やリスク要因を以下にご紹介します。
肥満・首まわりの脂肪
体重増加や肥満によって首まわりに脂肪がつくと、気道が圧迫されやすくなります。とくに日本人は顎が小さい傾向があり、やせていても気道が狭くなりやすい体質です。
あごや顔の骨格
下あごが小さい・後退している、扁桃や舌が大きいなどの解剖学的な特徴も、気道をふさぎやすくする原因です。遺伝的な要素も関与します。
加齢
年齢を重ねると、喉まわりの筋肉がゆるみやすくなり、睡眠中に気道が閉じやすくなります。中高年になるとSASの発症率が上がるのはこのためです。
飲酒・睡眠薬の使用
アルコールや睡眠導入剤は、喉の筋肉を緩めて気道をふさぎやすくするため、いびきや無呼吸を悪化させる原因になります。
鼻づまり・アレルギー性鼻炎
慢性的な鼻づまりや鼻炎によって口呼吸が習慣化すると、喉の奥が狭まり、無呼吸のリスクが高まります。
男性であること
男性は女性に比べて、もともと喉まわりの筋肉が厚く、舌も大きい傾向があります。そのため、睡眠中に気道がふさがれやすく、女性よりも睡眠時無呼吸症候群を発症しやすいとされています。また、男性ホルモンには筋肉を強く保つ作用がありますが、それが加齢で減少すると気道の弾力が失われ、リスクがさらに高まることもあります。
喫煙習慣
仰向けに寝ると、重力の影響で舌が喉の奥へ落ち込みやすくなり、気道がふさがれやすくなります。とくに、もともと舌が大きい方や下あごが小さい方は、横向きで寝た方が無呼吸の発生を防ぎやすいとされています。
仰向けで寝る習慣
アルコールや睡眠導入剤は、喉の筋肉を緩めて気道をふさぎやすくするため、いびきや無呼吸を悪化させる原因になります。
更年期以降の女性
女性は閉経前までは女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の働きにより、呼吸筋が保たれていてSASの発症リスクが比較的低いとされています。しかし、更年期以降にホルモンバランスが変化すると、喉まわりの筋力が低下し、気道が狭まりやすくなります。そのため、中高年以降の女性でも睡眠時無呼吸症候群を発症するケースが増えてきます。
睡眠時無呼吸症候群が引き起こす主な病気
単なる「いびき」では済まされない理由
肥満は下記のように様々な病気の引き金になります。
間違った方法で体重減少させると、健康を害する恐れがあるため、肥満が気になる方は当院の肥満外来に一度ご相談ください。医師のサポートのもと適切にダイエットして肥満解消を目指し、病気を予防しましょう。
高血圧
睡眠中に呼吸が止まるたびに交感神経が刺激され、血圧が急激に上昇します。これが慢性化すると、起きている間も高血圧状態が続くようになり、治療抵抗性高血圧の原因にもなります。
心不全・不整脈・心筋梗塞
酸素が不足することで心臓に強い負担がかかり、心房細動などの不整脈や心不全のリスクが上昇します。重度のSASは、突然死のリスクを高めるとも言われています。
脳卒中
無呼吸による血圧の急上昇・血管の損傷・動脈硬化の進行が重なると、脳出血や脳梗塞など脳血管障害の発症リスクが高まります。SASの方は、脳卒中を起こす確率が高いという研究もあります。
2型糖尿病
無呼吸による断続的な低酸素状態は、インスリンの働きを悪化させ、血糖値を上昇させやすくなります。また、睡眠の質が下がることでホルモンバランスが崩れ、糖尿病の発症・悪化につながります。
脂質異常症・メタボリックシンドローム
SASは、血中の中性脂肪や悪玉コレステロールの増加とも関連しており、動脈硬化や心血管疾患のリスクを高める要因となります。肥満・高血圧・高血糖・脂質異常が重なる「メタボ体質」とも密接に関係しています。
日中の強い眠気による事故リスク
睡眠の質が悪いと、日中に強烈な眠気が襲うようになります。これは重大な交通事故や労働災害の原因にもなり得ます。とくに運転業務に従事されている方には注意が必要です。
「生活習慣病」との相互悪化ループに注意
睡眠時無呼吸症候群は、肥満や高血圧などの生活習慣病の原因になるだけでなく、すでに生活習慣病を持つ方では、SASの重症化リスクも高まるという相互関係があります。
「いびきは放置してはいけない」と言われるのは、このようにさまざまな慢性疾患の引き金にもなり得るためです。
ご自身やご家族に該当する症状がある方は、健康を守るためにも早めの検査をおすすめします。
睡眠時無呼吸症候群は何科を受診すべき?
「いびきがひどい」「日中に強い眠気がある」「呼吸が止まっていると指摘された」 このような症状がある場合、何科を受診すればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、呼吸器だけでなく、循環器、代謝、神経、内分泌など、全身の健康に関わる病気であるため、複数の専門分野の視点が必要です。一般的には以下の診療科が対応しています。
睡眠時無呼吸症候群に対応する主な診療科
- 呼吸器内科:空気の通り道(気道)の構造異常や機能の評価、CPAP治療などを行います
- 循環器内科:高血圧や心不全、不整脈など合併症の評価・治療を行います
- 内分泌内科/糖尿病内科:肥満や糖尿病、メタボリックシンドロームとの関連に注目し、生活習慣の改善や薬物治療を行います
- 総合内科:多角的な視点で、他の病気の見逃しを防ぎながら総合的に評価します
当院では、専門医による多角的な診断・治療をワンストップで対応
当院では、睡眠時無呼吸症候群の検査・診断から生活習慣病まで、全身の状態を総合的に評価し、トータルでサポートできる体制を整えています。
- 循環器専門医
- 総合内科専門医
- 呼吸器専門医
- 内分泌代謝科専門医
- 糖尿病専門医
これら複数の専門領域をもつ医師が連携し、見落としのない精密検査・的確な診断・適切な治療計画を行います。
当院の睡眠時無呼吸症候群外来
 当院では、ご自宅で実施できる簡易睡眠検査(SASスクリーニング検査)をはじめ、必要に応じて精密検査やCPAP療法の導入・継続管理まで一貫して対応します。また、睡眠時無呼吸症候群と密接に関わる高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病に対しても、専門的な検査・治療を受けていただけます。
当院では、ご自宅で実施できる簡易睡眠検査(SASスクリーニング検査)をはじめ、必要に応じて精密検査やCPAP療法の導入・継続管理まで一貫して対応します。また、睡眠時無呼吸症候群と密接に関わる高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病に対しても、専門的な検査・治療を受けていただけます。
「何科に行けばいいか分からない」という方も、どうぞご安心ください。
上町はまのクリニックでは、専門性と総合力を活かした診療体制で、あなたの健康を全方位からサポートいたします。
自宅でできる睡眠時無呼吸症候群の検査
睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる場合、専門の検査によって無呼吸や低呼吸の有無・重症度を調べることが大切です。
「でも、入院や検査入院は大変そう…」という方もご安心ください。
上町はまのクリニックでは、ご自宅でできる簡易検査(スクリーニング検査)を実施しています。病院に泊まる必要はなく、ご自宅でいつものように眠るだけで検査が可能です。
自宅で行う睡眠時無呼吸検査(簡易検査)とは?
小型の検査機器を一晩装着して眠ることで、以下の項目を自動的に記録します。
- 呼吸の状態(無呼吸・低呼吸の回数)
-
血中の酸素濃度(SpO₂)
-
いびきの有無
- 睡眠中の体動など
この検査によって、睡眠時無呼吸症候群の可能性や重症度を簡単に評価することができます。
当院の治療内容
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療は、症状の重症度や体質、生活習慣などに応じて方針が異なります。
上町はまのクリニックでは、循環器・呼吸器・内分泌・糖尿病などの専門医が連携し、患者様一人ひとりに合わせた最適な治療プランをご提案しています。
軽度〜中等度の方へ
生活習慣の改善
- 減量(体重のコントロール)
- 禁酒・禁煙
- 就寝時の姿勢の工夫(横向き寝)
- 鼻詰まりやアレルギーの治療
生活習慣の見直しだけで、症状が大きく改善することもあります。 当院では、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の管理に加え、メディカルビル内に併設されたメディカルフィットネスを活用し、運動による無理のない減量・体力づくりを専門的にサポートしています。運動が苦手な方や持病をお持ちの方でも、医師の指導のもと、安全に取り組める環境が整っています。
中等度~重度の方へ
CPAP(シーパップ)療法
もっとも一般的かつ効果的な治療法です。 就寝中に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道の閉塞を防いで無呼吸を改善します。 CPAP療法を行うことで、以下のような改善が期待できます。
- いびきや無呼吸の解消
- 日中の眠気や倦怠感の改善
- 高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスク低下
- 心血管疾患や脳卒中の予防
当院では、導入から機器管理、定期的なフォローアップまで一貫してサポートしています。
睡眠時無呼吸症候群の対策と予防
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、「治療する病気」であると同時に、「予防できる病気」でもあります。また、治療中の方も生活習慣を見直すことで、無呼吸の軽減や将来的な合併症の予防が可能です。以下に、SASの予防や再発防止に役立つポイントをご紹介します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、「治療する病気」であると同時に、「予防できる病気」でもあります。また、治療中の方も生活習慣を見直すことで、無呼吸の軽減や将来的な合併症の予防が可能です。以下に、SASの予防や再発防止に役立つポイントをご紹介します。
適正体重の維持(減量)
もっとも効果が高い対策のひとつです。
肥満、特に首まわりや内臓脂肪の増加は、気道を圧迫し無呼吸を引き起こす大きな要因になります。
無理のないペースで体重を減らすことで、いびきや無呼吸の改善が期待できます。
当院では、管理栄養士の食事指導や、メディカルフィットネスを活用した運動プログラムを通じて、医師のサポートのもと、効果的かつ安全な減量をサポートしています。
飲酒・喫煙を控える
アルコールや睡眠薬は、喉まわりの筋肉をゆるめて気道をふさぎやすくします。
また、喫煙は気道の炎症を引き起こし、慢性的な鼻づまりやいびきを悪化させることもあります。
可能であれば、これらの習慣は見直しましょう。
寝る姿勢を見直す
仰向けで寝ると、舌が喉の奥に落ち込みやすくなり、気道がふさがれやすくなります。
横向き寝にすることで、無呼吸の回数が減るケースも多く見られます。
抱き枕などを使って寝姿勢を安定させるのもおすすめです。
鼻の通りを良くする
アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、慢性的な鼻づまりがあると口呼吸になり、いびきや無呼吸が悪化しやすくなります。
必要に応じて耳鼻科治療を受けたり、寝室の加湿・空気清浄にも配慮しましょう。
生活習慣病の管理を徹底する
SASと高血圧・糖尿病・脂質異常症は密接に関連しています。
血圧や血糖のコントロールが不十分だと、無呼吸が悪化することもあります。
逆に、SASを改善するとこれらの数値も安定しやすくなるという好循環が期待できます。
当院では、各分野の専門医が在籍しており、SASと関連する生活習慣病の管理を一貫して行えます。
定期的な検査・経過観察
治療をしていても、ライフスタイルや体重の変化によって症状が再発することもあります。
とくにCPAP療法を受けている方は、機器の調整や使用状況の確認、合併症チェックを含めた定期受診が大切です。
「ただのいびきだから」と軽く見てしまうと、心臓や脳の病気、生活習慣病の悪化へつながる恐れがあります。
当院では、早期のスクリーニング検査から予防・再発防止まで一貫してサポートしています。 「最近いびきが気になる」「日中の眠気がつらい」そんな方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
よくある質問
睡眠時無呼吸症候群は女性にも多い病気ですか?
はい。特に更年期以降の女性ではホルモンバランスの変化により発症しやすくなります。女性は「いびきが少ないタイプ」もあるため、気づかれにくい傾向があります。
「いびきがないのに眠い」のは睡眠時無呼吸症候群の可能性がありますか?
あります。いびきをかかないタイプのSASもあり、「眠っているのに疲れが取れない」「日中に眠くなる」といった症状が特徴です。
睡眠時無呼吸症候群の検査や治療は健康保険が適用されますか?
はい。簡易検査・精密検査・CPAP療法はいずれも保険適用です。当院でも保険診療で対応しております。
CPAP治療をやめることはできますか?
体重減少や生活習慣の改善により無呼吸が軽度になれば、CPAPを中止できるケースもあります。ただし自己判断は危険ですので、医師の指導のもとで判断します。
睡眠時無呼吸症候群は自然に治ることはありますか?
一時的に症状が軽減することはありますが、自然に完治することはほとんどありません。特に中等度以上は治療が必要です。
睡眠時無呼吸症候群は子どもにも起こりますか?
はい。小児SASは扁桃肥大やアデノイド肥大が原因になることが多く、学力低下や成長障害のリスクもあるため早期の対応が必要です。
睡眠時無呼吸症候群は妊娠に影響しますか?
妊娠中のSASは高血圧症候群や胎児の発育遅延を引き起こすことがあり、注意が必要です。妊娠中のいびきが急に増えた場合は、医療機関へ相談を。
マウスピース治療(口腔内装置)は保険適用ですか?
軽度〜中等度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対しては、保険適用でマウスピース治療を受けられる場合があります。対応歯科をご案内いたします。
CPAPは一生つけなければいけないのですか?
必ずしも一生ではありませんが、継続使用が重要です。中断するとすぐに症状が再発することが多く、合併症のリスクが高まります。
睡眠時無呼吸症候群は仕事中の事故リスクと関係しますか?
はい。SASによる強い眠気は居眠り運転や作業ミスの原因になります。特に運転業務に従事されている方は早期診断・治療が重要です。
睡眠時無呼吸症候群はがんと関係がありますか?
一部の研究では、慢性的な低酸素状態ががん細胞の活性化と関連する可能性が示唆されています。引き続き研究が進められています。
市販のいびき対策グッズで無呼吸症候群は改善しますか?
市販のいびき防止グッズはあくまで軽度のいびき対策です。無呼吸そのものを解消することはできないため、医療機関での検査をおすすめします。
睡眠時無呼吸症候群と耳鳴りやめまいは関係がありますか?
間接的な関係がある可能性があります。自律神経の乱れや血流低下が原因で、耳鳴り・頭痛・めまいなどが生じるケースがあります。
睡眠時無呼吸症候群の人は寝言や夢が増えますか?
無呼吸による中途覚醒が頻繁に起きると、浅い睡眠が増えて夢を見やすくなる場合があります。ただし、夢の多さ=SASとは限りません。