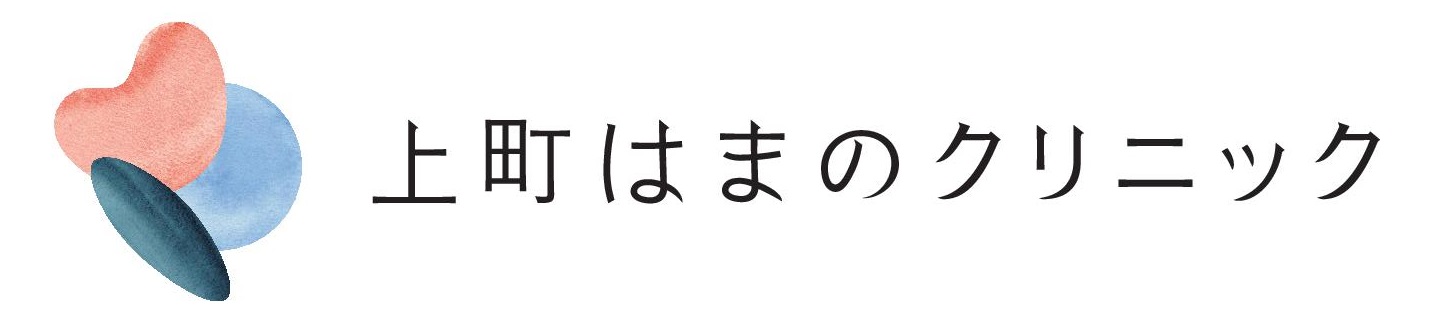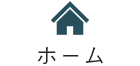骨粗鬆症とは
 骨粗鬆症は、骨密度の低下や骨の質の低下によって骨折しやすくなる病気です。発症すると骨が脆弱になり、くしゃみや転んで肘や手を付いただけで骨折してしまう恐れがあります。骨は、破骨細胞という細胞によって古い骨が吸収される「骨吸収」と骨芽細胞という細胞が成長して新たな骨になる「骨形成」のバランスによって維持されており、骨吸収が多くなると骨密度が低下して骨粗鬆症を発症します。骨粗鬆症は脳卒中、がん、心筋梗塞といった命に関わる疾患の直接の原因となることはありません。しかし、骨折すると日常生活が制限され、重症な場合は寝たきりになることもあります。寝たきり状態は生活習慣病の悪化や肺炎の発症など、他の病気の発症させ、悪化させる大きなリスクとなるため、予防のための治療が重要です。骨密度の低下は自覚症状なく進行し、骨折して初めて発覚することもあるので、定期的に骨密度検査を受けて骨の状態を把握することが大切です。
骨粗鬆症は、骨密度の低下や骨の質の低下によって骨折しやすくなる病気です。発症すると骨が脆弱になり、くしゃみや転んで肘や手を付いただけで骨折してしまう恐れがあります。骨は、破骨細胞という細胞によって古い骨が吸収される「骨吸収」と骨芽細胞という細胞が成長して新たな骨になる「骨形成」のバランスによって維持されており、骨吸収が多くなると骨密度が低下して骨粗鬆症を発症します。骨粗鬆症は脳卒中、がん、心筋梗塞といった命に関わる疾患の直接の原因となることはありません。しかし、骨折すると日常生活が制限され、重症な場合は寝たきりになることもあります。寝たきり状態は生活習慣病の悪化や肺炎の発症など、他の病気の発症させ、悪化させる大きなリスクとなるため、予防のための治療が重要です。骨密度の低下は自覚症状なく進行し、骨折して初めて発覚することもあるので、定期的に骨密度検査を受けて骨の状態を把握することが大切です。
骨粗鬆症の原因は?
加齢
加齢とともに以下のような理由で破骨細胞が活性化し、骨密度が低下すると言われています。
- 骨髄中の骨芽細胞の減少
- 女性ホルモン分泌の低下
- 腸管でのカルシウム吸収の低下
- 血中カルシウム濃度を維持するビタミンD活性の低下
- 食事からのカルシウム摂取量の低下
- 慢運動不足
閉経してからの
女性ホルモンの減少
骨粗鬆症は女性がかかりやすい病気とされ、患者さまの80%以上が女性であるとされています。エストロゲンは女性ホルモンの1つで、骨代謝において破骨細胞の形成を抑制する作用があります。女性は閉経後にエストロゲンの分泌が低下するため、破骨細胞による骨吸収が進み、同じ年代の男性より骨密度の低下が顕著に見られます。
運動不足などの不規則な生活や過度なダイエットによる栄養の偏り
あまり外出しないで家にいることが多い人は、皮膚に日光が当たることにより作られるビタミンDが不足しやすくなります。また、運動して骨に負荷をかけることにより骨形成が活発になるので、運動不足も骨密度低下の原因になります。さらに、アルコールの過剰摂取やタバコをよく吸う人も骨粗鬆症にかかる可能性は高いため、摂取する量を自分で調整して病気を予防する必要があります。また、ダイエットによって栄養が偏ると、骨粗鬆症のリスクが高まります。成長過程の子どもはカルシウムを溜め込んで丈夫な骨を作る大事な時期のため、この時期に行った過度なダイエットが原因で、大人になってから骨密度が低下する可能性があります。
お薬の副作用や病気の
影響
骨粗鬆症は、服用中のお薬や一部の病気から引き起こされる場合もあります。例えば、関節リウマチ、内分泌疾患(副甲状腺機能亢進症など)、生活習慣病(糖尿病など)が原因で発症するケースが多いことが分かっています。
薬の副作用で骨粗鬆症を発症する場合もあります。原因として多く見られるのが、ステロイドの長期投与によるものです。ステロイドを3ヶ月以上服用している方は、定期的な骨密度の測定や、必要に応じて予防的に骨粗鬆症の薬を服用することが望ましいとされています。
骨粗鬆症の症状
骨密度の低下は症状が現れないまま進行していきます。骨密度が低下して、転んだ時に足を骨折したり、腰を曲げた時に脊椎が圧迫骨折を起こしたりして初めて痛みなどの骨折による症状が出てきます。そのほかに、骨粗鬆症になりやすい体の状態を示している可能性がある症状には、以下の様なものが挙げられます。
- あまり食べていないのに満腹になる
- 3㎝以上身長が小さくなった
- よく着ていた服のサイズが合わなくなった
- 立つ時や重い物を持つ時に腰や背中が痛い
- 息切れしやすい
- 腰や背中が丸くなってきた
骨粗鬆症の検査
 当院では、2種類のX線を照射し、吸収率の差によって骨密度を測定するDEXA法を用いた骨密度測定器を導入しています。照射するX線の量はごくわずかであり、測定も迅速に行うことができます。さらに、簡易的には骨密度は踵の骨や手首の骨で測定されることが多いですが、当院の機器では腰(腰椎)と股関節の骨(大腿骨頸部)という、骨折した際に重症化する部位の骨密度を測定することにより、より正確に骨粗鬆症を診断できます。日本骨粗鬆症学会のガイドラインで、骨粗鬆症を診断するためには、腰椎および大腿骨頸部での骨密度測定が奨励されています。
当院では、2種類のX線を照射し、吸収率の差によって骨密度を測定するDEXA法を用いた骨密度測定器を導入しています。照射するX線の量はごくわずかであり、測定も迅速に行うことができます。さらに、簡易的には骨密度は踵の骨や手首の骨で測定されることが多いですが、当院の機器では腰(腰椎)と股関節の骨(大腿骨頸部)という、骨折した際に重症化する部位の骨密度を測定することにより、より正確に骨粗鬆症を診断できます。日本骨粗鬆症学会のガイドラインで、骨粗鬆症を診断するためには、腰椎および大腿骨頸部での骨密度測定が奨励されています。
検査は、専用の服装に着替え、検査台に仰向けになってから約10分で検査は終了します。検査当日に結果が判明し、ご説明まで行います。検査結果によって治療が必要になった方には、お薬の服用など患者さまに応じた適切な治療方法を決めていきます。
骨粗鬆症の治療
薬物療法
薬物療法では、骨吸収阻害剤、ビタミンDやカルシウム製剤、女性ホルモンの作用を増強させる薬剤などの内服薬、カルシトニン製剤や副甲状腺ホルモンの注射などで改善を図ります。どの薬剤を選択するかは、患者さま一人ひとりに合わせて選択していきます。
中には重篤な副作用の可能性をもつ薬剤もありますが、副作用のリスクを含めた患者さまの健康状態を適切評価させていただくことにより、副作用の可能性は減らすことができます。
骨折を起こす前から予防的に治療を開始する場合は、治療の意義が理解しにくいかもしれません。そのような患者さまにも必要性を十分に説明した上で治療を開始いたします。
下記では、薬物療法で使用されることが多いお薬を解説します。
骨吸収を防ぐ薬
ビスホスホネート薬
破骨細胞の働きを抑制し、骨が壊されるのを防ぎます。週に1回、月に1回など服用する頻度が薬剤によって異なります。また、起床時にコップ1杯以上の水でしっかりと飲み込んでいただくことが必要な薬です。
カルシトニン製剤
血中に骨のカルシウムが溶け出すのを抑制し、痛みを緩和する効果が期待できる注射製剤です。
デノスマブ[新薬]
破骨細胞が働くために不可欠なタンパク質に作用して骨吸収を抑制する、半年に1回投与する注射製剤です。
骨形成を促進する薬
副甲状腺ホルモン薬
一般名:テリパラチド[新薬]
骨を生成する骨芽細胞を活性化させる、副甲状腺ホルモン製剤です。皮下注射で投与します。
その他
カルシウム薬
活性化ビタミンD薬
ビタミンK薬
食事療法
新しい骨の形成を促す栄養素であるビタミンD、カルシウム、ビタミンKなどをよく摂取してください。ビタミンDは魚やキノコ類に多く含まれます。またビタミンDとカルシウムを一緒に摂取すれば、腸管でよりカルシウムを吸収しやすくなります。
ビタミンKは緑黄色野菜や果物に多く含まれます。さらに、骨密度を維持するためには運動をすることも重要です(後述)。運動を習慣的に継続するためには筋肉量を維持することが重要です。そのため、タンパク質を積極的に摂ることが大切です。栄養バランスを整え、カロリーが多くなりすぎないように意識し、規則正しい食生活を心がけましょう。
運動療法
年齢や体格、健康状態に応じて、自分に合った運動メニューをこなすようにしましょう。無理な運動は怪我に繋がる恐れがあるので、注意する必要があります。
ウォーキング、サイクリング、ジョギング、水泳、グラウンドゴルフ、テニス、卓球、体操などが推奨されています。運動が苦手な人でも歩くだけでできるウォーキングがお勧めですが、無理しない程度の運動であれば何でも挑戦してみてください。ライフスタイルや嗜好にあった運動を、軽く汗ばむ程度の強度で、長く続けることが何より肝心です。
運動と骨密度の深い関係
運動と骨密度は深い関わりがあります。
適度な運動の継続により、骨にカルシウムが沈着しやすくなり、骨芽細胞の動きが盛んになり、新しい骨が作られやすくなります。また、太陽の光を浴びて、体の中でビタミンDを生成させることも大切です。ビタミンDの働きにより、カルシウムの吸収が促され、骨芽細胞を活性化させることにより骨形成が促進します。家にこもりがちの人は太陽の光や運動が不足することにより、筋肉が衰えて転びやすくなり、骨密度も低下することにより、骨粗鬆症のリスクが高くなります。。
閉経を迎えた女性は特に骨量が低下するため、ご高齢の方は骨密度を定期的に測定し、骨の状態をチェックして骨折の予防に努めましょう。
骨粗鬆症は予防できるの?おすすめの食べ物は?
骨粗鬆症は、骨折を起こす前に病状の進行を防ぐことが大切です。カルシウム以外にも、ビタミンD、ビタミンK、グネシウム、リン、適量のタンパク質を積極的に摂取し、病気を予防しましょう。
骨粗鬆症予防におすすめの食品
カルシウム
体内のカルシウムの99%は、骨や歯の成分となりますが、筋肉や血液の中にもカルシウムは含まれており、ホルモンの分泌、神経伝達への働きかけ、止血、筋肉の収縮などに関与しています。
そのため、体内のカルシウムが不足した場合、骨粗鬆症以外にも様々な体調不良を引き起こします。
牛乳、小松菜、ししゃも、プロセスチーズなどのカルシウムが豊富な食品を積極的に摂取しましょう。カルシウムは腸で吸収されており、朝食で牛乳や乳製品を食べるとより吸収されやすくなるのでお勧めです。
タンパク質
骨の主成分の1つにタンパク質があります。骨を支えるコラーゲンのもとになり、内臓、筋肉、爪、皮膚などを作り出す非常に重要な成分です。
若い頃は動物性たんぱく質を食べることが多いですが、年を取るにつれてタンパク質は不足しがちになります。タンパク質が含まれる牛乳、胸肉、魚、乳製品、大豆(特に納豆)などを意識して摂取することが必要です。
ビタミンD
血液に含まれるカルシウム濃度を維持するのに欠かせないのがビタミンDです。積極的にカルシウムを食べても、ビタミンDが足りなければカルシウムの吸収率は上がらないため、ビタミンDとカルシウムを一緒に摂取するのがお勧めです。鮭や青魚(いわし、さんま、さばなど)、キノコ類、卵に多く含まれるので、よく食べるようにしましょう。
また、日光浴をすると主に紫外線の働きにより皮膚でビタミンDが作られます。太陽の光に1日約15分あたれば、1日に必要なビタミンDを補えるとされています。太陽が出ている日に、木の陰にいるだけでも問題ありません。なお、家の中にいて窓ガラス越しに日光を浴びても、紫外線は肌まで届かないので注意しましょう。外で洗濯物干す、買い物などでもビタミンDが生成されます。日焼け止めを肌に塗布している場合、日光浴の時間を少し長くしましょう。
ビタミンK
骨にはオステオカルシンというタンパク質が含まれており、カルシウムが溶け出すのを抑制する、骨にカルシウムが付くのを促すといった働きがあります。
このオステオカルシンの働きを活性化するのがビタミンKです。そのほかにも、骨に含まれるタンパク質であるコラーゲンを作り出すために働きかけたり、血を固めて止血を補助したりする作用があります。ビタミンKが足りないと、骨は脆弱化し、骨折しやすくなるので注意が必要です。
モロヘイヤ、納豆、小松菜、のりに多く含まれています。
マグネシウム
ミネラルの一種であるマグネシウムは、様々な酵素を活性化させる役割を担っています。神経の興奮の抑制や体温・血圧の調整にも役立っており、生きていく上で不可欠と言えます。人の体に存在するマグネシウムの50~60%は骨に含まれ、カルシウムをよく摂ってもマグネシウムが足りないと、血中のカルシウムが不足します。このように、カルシウムとマグネシウムは深い関係性があるのです。
マグネシウムは、海藻類、魚介類、ほうれん草、大豆製品(納豆)、ごま等に豊富に含まれています。マグネシウムとカルシウムがともに豊富に含まれるひじきや昆布はお勧めです。
過剰摂取を避けた方が
よい食品や嗜好品
リンを多く含む加工食品、炭酸飲料やアルコールの過剰な摂取は骨代謝に悪影響を及ぼします。
喫煙はビタミンDやカルシウムの吸収を妨げるため、骨密度を低下させる可能性があります。
また、喫煙による血流障害や低酸素状態は骨折の治癒や骨形成を妨げる可能性があります。