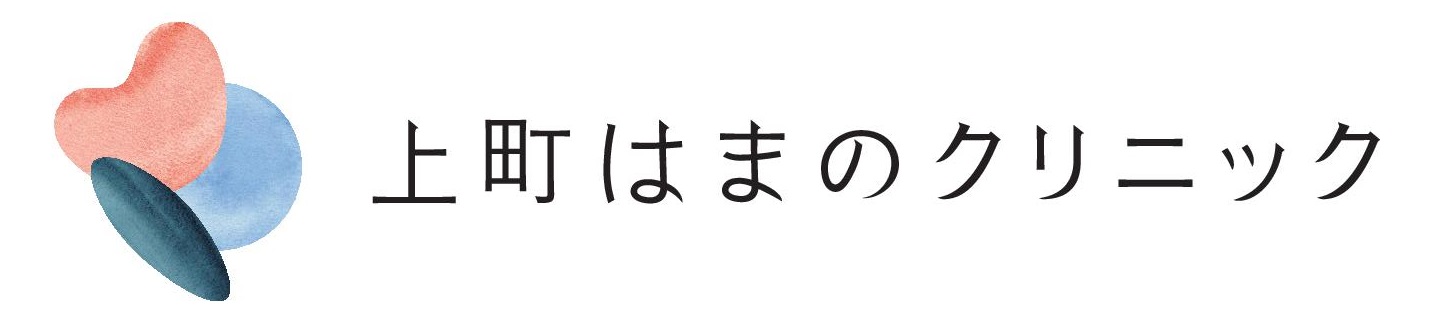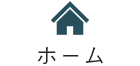心臓リハビリテーション
とは
 心臓リハビリテーションは、心臓や血管の病気をお持ちの方にお薬を使用するのではなく、生活習慣改善のアドバイスや運動療法などで症状改善を図る治療法です。心筋梗塞、狭心症、閉塞性動脈硬化症、心不全といった病気を持つ方が対象です。年をとるにつれて心臓や血管の病気は悪化しやすくなるため、病気の予防や進行の抑制、何回も入院したり症状を繰り返したりするリスクも軽減できます。しかし、心臓リハビリテーションで心臓や血管の病気を治療する病院はまだまだ少ないです。
心臓リハビリテーションは、心臓や血管の病気をお持ちの方にお薬を使用するのではなく、生活習慣改善のアドバイスや運動療法などで症状改善を図る治療法です。心筋梗塞、狭心症、閉塞性動脈硬化症、心不全といった病気を持つ方が対象です。年をとるにつれて心臓や血管の病気は悪化しやすくなるため、病気の予防や進行の抑制、何回も入院したり症状を繰り返したりするリスクも軽減できます。しかし、心臓リハビリテーションで心臓や血管の病気を治療する病院はまだまだ少ないです。
当院は循環器内科専門医師や理学療法士、健康運動指導士、看護師が連携し、患者さまの年齢や運動能力、症状に合わせた有酸素運動や筋力トレーニングのメニューをご提案いたします。週2~3回ほど当院にお越し頂いて、作成した運動メニューを続けてこなして頂き、健康な方と変わらない生活や社会復帰を目標とします。
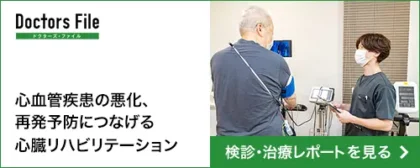
心臓リハビリテーションはこのような方に
おすすめです
- 心臓の病気があるため、外に出かける(旅行、遠出など)のが心配な方
- 心臓の病気があるため、運動や生活の中で体を動かすのが心配な方
- 心臓の病気で入院や手術を受けた方
- 理学療法士・健康運動指導士から自分に合った運動やリハビリのアドバイスを受けたい方
- 管理栄養士から食生活のアドバイスを受けたい方
- 倦怠感、動悸、息切れといった症状があるのに、検査で心臓の異常が発見されなかった方
心臓リハビリテーションの適応
- 狭心症・急性心筋梗塞
- 慢性心不全
- 末梢動脈閉塞性疾患
- バイパス手術後/弁膜症手術後/経カテーテル大動脈弁置換術後
- 大動脈解離、大動脈瘤の手術後またはステントグラフト内挿術
- 不整脈、デバイス植込み後(心不全を伴うもの)
- 肺高血圧症(心不全を伴うもの)
- 心臓移植後
心臓リハビリテーションの効果
- 運動で体内の酸素量を増加させます。
- 自律神経のバランスが良くなり、血圧や脈拍の安定に繋がります。
- 運動機能の回復によって運動しやすくなります。
- 血管内皮機能という血管の拡張する力が向上して、血行促進の効果が期待できます。
- うつ症状や不安感の軽減の期待ができます。
- 血が止まりやすくなり、血栓ができにくくなります。
- 心不全や狭心症の症状の改善が期待できます。
- インスリンの効果が得られやすくなるため、血糖値の改善が見込めます。
- 心筋梗塞の症状が現れるのを軽減できます。
心臓リハビリテーションの内容
検査
体組成測定(Inbody)・初回のみ
体にわずかな電気を流し、電気の抵抗性であるインピーダンス(電気の流れやすさ)を測定することで、体脂肪率を算出する方法です。人電解質が豊富な骨や筋肉などは電気を通しやすいですが、体脂肪は電気を通しません。この特性を活用して、体に電気を流してその抵抗性を測定し、身長と体重を照らし合わせて体脂肪率を推測します。
心肺運動負荷試験(CPX)
心肺運動負荷試験(CPX)は、血圧、心電図、呼気ガス(マスク着用)を測りつつ、ペダルが少しずつ重くなる自転車をこいで頂く運動負荷検査の1つです。
心臓疾患がある場合も、心臓への負担がかかり過ぎない程度の運動強度(AT:嫌気性代謝閾値)を測り、患者さまにお伝えすることが可能です。
心肺運動負荷試験(CPX)の結果から、心臓リハビリのための運動メニューをご提案させて頂き、運動療法を実施いたします。
運動療法
理学療法士や健康運動指導士などからサポートを受けつつ、心臓の負荷がかからない程度の運動メニューをこなし、心臓の働きを活発化させます。運動療法により、心臓の病気が再発するのを防ぐことが期待できます。歩行練習、筋力トレーニング、エアロバイクといった様々な運動をサポートいたします。
食事療法
医師や看護師のアドバイスのもと、栄養に偏りがなく、エネルギーも適正な食生活への改善を目指します。患者さまが適切な食生活を長く続けられるように、生活習慣やご家庭の状況などを考えた食事内容の指導を行います。
心臓リハビリの通院期間と費用(保険適用)
 心臓リハビリを始めて150日間は保険で治療できます。心臓リハビリには、週に1~3回ほどを目安に通院して頂きます。なお、医師の判断や症状の進み具合から、150日以上かかるケースもあります。
心臓リハビリを始めて150日間は保険で治療できます。心臓リハビリには、週に1~3回ほどを目安に通院して頂きます。なお、医師の判断や症状の進み具合から、150日以上かかるケースもあります。
ご不明な点は、お電話もしくは下記フォームよりお問い合わせください。